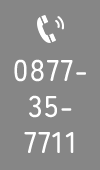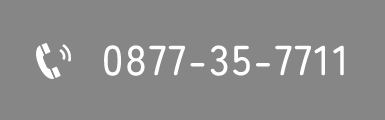白内障の症状チェック
初期症状
 白内障は初期には自覚症状はほとんどなく、外見上の変化もありません。
白内障は初期には自覚症状はほとんどなく、外見上の変化もありません。
通常はゆっくりと進行していくため、気づかずに進行してしまうこともあります。進行すると、ぼやける、かすむ、光を眩しく感じる、2重3重にみえる、などの症状が現れます。少しでも気になる症状がある場合は、丸亀市郡家町のひらの眼科へご相談ください。
進行時の症状
 白内障が進行すると、以下のような症状が現れます。
白内障が進行すると、以下のような症状が現れます。
ゆっくり進行するため、見え方が悪化していても気づかないケースもあります。気づかないうちに車の運転や階段の昇り降りなどの日常生活に危険を伴うようになることもあるため、定期的な眼科検診をおすすめします。
- 物がかすんで見える、ぼやけて見える
- 明るい場所では光が眩しく感じる
- 眼鏡やコンタクトレンズが合わなくなる
- 物が二重三重に見える
- 目の疲れを感じやすくなる
見え方
 正常の見え方
正常の見え方
 進行した際の見え方
進行した際の見え方
水晶体が白く濁る
「白内障」とは?
白内障は、レンズの役割を果たす水晶体が、様々な原因で白く濁ってしまう病気です。
水晶体の濁りが進行すると、目に入った光が水晶体の中で散乱するために見えづらくなります。
白内障の原因は大きく分けて先天性と後天性に分けられますが、後天性の白内障はさらに以下の6種類に分類されます。
加齢性白内障
白内障の中で最も多いのは、加齢性白内障です。加齢性白内障は老化現象の一種ですので、個人差はありますが、年齢を重ねるとともに誰にでも生じます。白内障の症状は早くて40代から現れ、80歳以上ではほぼ全員に白内障の症状が現れるとされています。
併発白内障
併発白内障とは、他の目の病気に合併する白内障のことです。白内障を併発する目の病気には、ぶどう膜炎や緑内障、網膜剥離、網膜変性症などがあります。
全身疾患に伴う白内障
目の病気だけでなく、糖尿病やアトピー性皮膚炎などの全身疾患に併発する白内障もあります。特に、アトピー性皮膚炎に合併して発症する白内障は、若い年代の方が多いのが特徴です。
薬物性白内障
薬物性白内障は、服用している薬剤が原因で発症する白内障です。最も多いのは、ステロイドの長期使用が原因となるケースです。薬物性白内障は進行が早く、数ヶ月から1年程度で手術が必要になる場合もあります。
外傷性白内障
外傷性白内障は、目に強い衝撃が加わって水晶体が傷つくことで発症する白内障です。水晶体の損傷の程度によっては、他の白内障に比べて症状が急速に進行する場合があります。一方で、ボールが目に当たるなどの打撲の場合は、年数が経過してから症状が現れることもあるため、注意が必要です。
その他の白内障
赤外線や放射線が原因で白内障になるケースもあります。
例えば、ガラス職人や溶鉱炉で働く方は強い赤外線を浴びるため、白内障になりやすいとされています。また、目の近くに放射線治療を受けている方も白内障になりやすいとされています。
加齢性白内障について
白内障の多くは加齢性白内障です。もともと透明な水晶体が、年齢を重ねるにつれて濁ってきます。
加齢性の白内障の発症には「酸化ストレス」「糖化ストレス」と呼ばれる現象が深く関わっています。
酸化ストレス
 わたしたちは呼吸によって得た酸素や、食事をして摂取した栄養素をもとに、生きていくうえで必要なエネルギーを作り出します。
わたしたちは呼吸によって得た酸素や、食事をして摂取した栄養素をもとに、生きていくうえで必要なエネルギーを作り出します。
エネルギーを作り出す際に、活性酸素という物質が作られてしまい、これが酸化ストレスの原因物質の1つです。
また、紫外線、喫煙、糖尿病なども酸化ストレスを増加させます。酸化ストレスは体中の老化現象と関係していますが、その1つが加齢性の白内障です。
酸化ストレスは水晶体のタンパク質の変性を引き起こし、濁りを生じさせます。
卵の白身はもともと透明ですが、熱による変性で白くなるのと同じ理屈です。
糖化ストレス
血液中の糖と、タンパク質が結合して産生される最終糖化産物(AGE)という物質があり、これが糖化ストレスの原因物質となります。
血液中に余剰な糖が多いとAGEが蓄積しやすくなり、白内障だけでなく体中の老化を引き起こします。
白内障が生じている水晶体にはAGEが多く蓄積しており、AGEが水晶体のタンパク質を変性させたり、酸化ストレスを増加させたりすることで水晶体が濁ってくると言われています。
糖尿病の方はそうでない方に比べて白内障になりやすいのはそのためです。甘いものや炭水化物をとりすぎず、バランスの良い食事を心がけましょう。
白内障の検査
 白内障の検査には、以下の検査があります。
白内障の検査には、以下の検査があります。
白内障の発症初期は自覚症状に乏しく、気がつかない内に進行してしまうことが多いため、何らかの自覚症状が現れたら、早めに受診して検査を受けることが重要です。
屈折検査
屈折検査によって、遠視・近視・乱視の種類や程度を測定します。
屈折検査の結果をもとに、視力検査を行います。
視力検査
どの程度視力が低下しているのかを把握するために、視力測定をします。裸眼の視力と矯正視力を測定し、両者を比較します。
眼圧検査
視力障害の原因が緑内障の可能性もあるため、眼圧を測定して、眼球内部の圧力に異常がないかを調べます。眼圧が正常値よりも高い場合は緑内障が疑われます。
細隙灯顕微鏡検査
細隙灯顕微鏡検査では、細い光を眼球に当てて顕微鏡で拡大し、眼球内部を詳しく調べます。水晶体の濁りがどの程度あるのかも調べます。
眼底検査
検査前に散瞳薬を点眼して一時的に瞳孔を開いた状態にし、眼底の状態を評価します。緑内障や眼底出血、網膜剥離など、白内障以外に病気が合併していないかを調べます。
光干渉断層計(OCT)検査
眼底の黄斑部や視神経乳頭に異常がある場合、白内障手術を行っても視力が改善しづらくなります。OCT検査でこれらの部分を詳細に調べることが可能です。黄斑部や視神経乳頭の異常の有無を調べることで術後の視力の予測が可能になります。
眼軸長検査(手術を受ける方のみ)
白内障の手術をする前に必要な検査です。眼内レンズの度数を決定するための眼軸長を測定します。眼軸長とは、眼球の前面にある角膜から、一番奥の網膜までの長さを指します。
角膜内皮細胞検査
(手術を受ける方のみ)
白内障の手術をする前に必要な検査です。黒目(角膜)の内側にある内皮細胞の減少の有無を調べます。角膜内皮細胞数が減少すると、本来透明な角膜に濁りが生じます。白内障の手術をすることで角膜内皮細胞にストレスがかかるため、手術前に十分な内皮細胞数があるか確認します。
採血(手術を受ける方のみ)
手術前の全身の状態や感染症の有無を調べます。全身状態が悪い場合、手術日程に変更が必要な場合があります。
白内障の治療方法
薬物療法(目薬)
 自覚症状がなく、日常生活に影響がない発症初期の段階では、目薬による治療を行います。ただし、濁った水晶体を元に戻すことはできないため、白内障の進行を遅らせることが治療の目的となります。
自覚症状がなく、日常生活に影響がない発症初期の段階では、目薬による治療を行います。ただし、濁った水晶体を元に戻すことはできないため、白内障の進行を遅らせることが治療の目的となります。
手術
 進行した白内障の症状により、日常生活に支障をきたす場合は、手術をすることが一般的です。
進行した白内障の症状により、日常生活に支障をきたす場合は、手術をすることが一般的です。
手術は点眼薬で局所麻酔をかけて行います。水晶体を包む袋をわずかに切開し、濁った水晶体を吸引して取り除き、水晶体の代わりに眼内レンズを挿入して固定します。
手術は入院せず、日帰りで行うことが多く、術前の準備や術後の説明などを含めてトータルで2時間程度かかりますが、手術自体は通常5-10分で終了します。
白内障の予防方法

白内障の主な原因は加齢であり、完全に予防することは難しいです。
しかし、日常生活上でいくつかの習慣を取り入れることで、酸化ストレスや糖化ストレスを減らし、白内障の予防効果が期待できます。
- 禁煙をする
- 帽子やサングラスを使用して、強い紫外線を避ける
- 過度な飲酒を避ける
- バランスの良い食事と適度な運動を心がけて、生活習慣病を予防する
白内障は一度発症すると治すことはできないため、予防が重要です。取り入れていない習慣があれば、日常生活にぜひ取り入れてみてください。