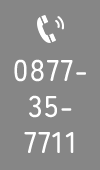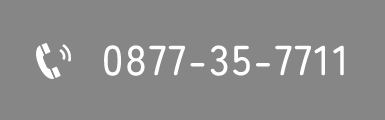一般眼科について
 一般眼科では、目の疾患や症状に対して、幅広く診断・治療します。
一般眼科では、目の疾患や症状に対して、幅広く診断・治療します。
具体的には、白内障、緑内障、網膜症、結膜炎、ドライアイ、霰粒腫・麦粒腫などの疾患の治療、また近視・遠視・乱視の矯正や、コンタクトレンズや眼鏡の処方等行います。
目の疾患は、早期発見・早期治療が重要です。不調を感じた時は、お早めにご相談ください。
このような症状は
ございませんか?
目(視界)がかすむ
白内障や緑内障、網膜の病気、老眼、ドライアイ、ぶどう膜炎などさまざまな目の病気が原因となります。近年、スマートフォンやパソコンの普及によって目を酷使している方も多く、一時的に調節力が低下し、目(視界)がかすむことがあります。まずは原因の検索が重要ですので、目を休めて改善しない場合はご相談ください。
目が赤い
目の充血は、白目全体が赤いケース(出血)と、細い血管が拡張しているケース(感染や炎症)の2つに大きく分けられます。
白目全体が赤くなる出血の場合、目をこするなどの刺激、高血圧の薬や抗凝固薬の内服などが原因として考えられますが、特に原因がないこともよくあります。基本的に緊急性はありませんが、症状が気になる方はご相談ください。
視力が落ちた
視力が落ちると、日常生活の様々な場面で不便が生じ、転倒などのリスクもあります。視力が落ちたと感じる場合、専門的な治療が必要な疾患が原因になっていたり、近視や乱視、老眼など眼鏡で対応が可能な状態であったり、様々な可能性が考えられます。早期の治療が必要な疾患の可能性もありますので、一度ご相談ください。
ゆがんで見える
物がゆがんで見える時は、黄斑前膜、黄斑円孔、加齢黄斑変性症、中心性漿液性網脈絡膜症、糖尿病性網膜症などが疑われます。これらの疾患では、いずれも網膜という神経の中心部(黄斑)に問題が生じて症状が現れます。早期診断・早期治療が望ましいため、早めにご相談ください。
目が乾く
目の乾きには、季節によるものやスマートフォンやパソコンによるもの、コンタクトレンズの使用によるものなど様々な原因があります。目の乾きは普段の生活を見直すことで改善する場合もありますが、ドライアイの場合には、点眼などを用いた治療が必要となります。症状が続くときは一度ご相談ください。
目がかゆい
目がかゆい時は、結膜という白目の表面や瞼の裏にある表面組織が炎症を起こしています。原因は様々ですがアレルギー性結膜炎が多いです。スギやヒノキに対するアレルギーの場合は春に痒みが強くなり、それ以外の季節は症状がない場合が多いのですが、ダニやハウスダストに対するアレルギーの場合は1年中痒みが続きます。また重症なアレルギー性結膜炎では、腫れた結膜と黒目(角膜)がこすれて角膜に傷がつくこともあります。いずれの場合も治療は、点眼薬などを用いた薬物療法が中心になります。また、痒みはアレルギー以外の感染性結膜炎でも生じることがあります。症状が続くときは一度ご相談ください。
目が痛い
目の痛みは、目の表面の痛みと目の奥の痛みに分けられます。前者はドライアイ、逆さまつげ、異物の混入などが主な原因です。後者は、視神経炎などの眼の病気だけでなく緊張性頭痛や片頭痛などの慢性頭痛の可能性があります。また、目の急激な痛みとともに吐き気や頭痛が見られる時には、急性緑内障発作も考えられます。急性緑内障発作は急激な眼圧の上昇によるものであるため、速やかに眼圧を下げる治療が必要です。ひどい痛み、充血や吐き気や視力低下を伴う場合は早めにご相談ください。
視野が狭くなった
視野が狭くなる代表的な目の病気には、緑内障や網膜剝離などがあります。緑内障は何ヶ月や何年もかけて少しずつ視野が狭くなっていくことが多いです。網膜剥離は日の単位、週の単位で急速に視野がせまくなります。これらの疾患の場合、放っておくと失明の可能性があるため、症状に気づいたら早めに受診しましょう。40歳以上の日本人の20人に1人は緑内障があると言われています。40歳以上の方は、緑内障の検診のために年に1回は眼底検査を受けることをおすすめします。
二重に見える
片方の目で見て二重に見える場合は、乱視、白内障、ドライアイ、眼精疲労などが原因として挙げられます。乱視はメガネで補正、白内障は手術治療、ドライアイは点眼治療を行うことが多いです。また、両方の目で見て二重に見える場合は、斜視が考えられます。斜視の場合は片目を手で覆うと二重にみえていたものが1つに戻るのが特徴です。斜視は、脳出血や脳梗塞などの緊急性の高い疾患が原因になっていることもあるため、早めに医療機関を受診しましょう。
一般眼科で対応可能な
疾患の例
近視・遠視・乱視・
斜視
近視・遠視・乱視は、目に入った光が網膜で正しく像を結ばない状態です。「屈折異常」とも呼ばれます。
屈折異常は眼鏡による治療を行うことが多いです。また、左右の目が違う方向を向いている場合は、斜視と言います。
患者様の目の状態やライフスタイルなど、お一人おひとりに合った適切な治療を行います。
結膜炎
結膜炎は、細菌やウイルス、アレルギーなどが原因で起こる結膜の炎症です。目の充血やかゆみ、めやに、目の痛み、異物感、瞼の腫れなどの症状が見られます。点眼薬や内服薬による治療を行います。
霰粒腫・麦粒腫
(ものもらい・めばちこ)
霰粒腫(さんりゅうしゅ)は、まぶたの中にあるマイボーム腺という分泌腺の出口が塞がることで、まぶたが腫れる状態です。通常は痛みを伴いません。麦粒腫(ばくりゅうしゅ)は、まぶたの分泌腺やまつげの毛根に細菌感染が生じ、まぶたが腫れ、痛みを伴います。霰粒腫には抗炎症薬の治療や手術による治療を、麦粒腫には抗菌薬による治療を行います。
ドライアイ
ドライアイは、加齢による涙の変化やスマートフォンを長時間見るなどのライフスタイルが原因で、眼球の表面が乾きやすくなる状態です。目の乾きだけでなく、かすみ、充血、目やに、異物感、流涙などさまざまな症状が見られます。
ドライアイは角膜が傷つきやすい状態で、そのままにしていると視力が低下する可能性があります。点眼薬などを用いた治療が必要です。
白内障
白内障は、主に加齢が原因で目の中のレンズ(水晶体)が濁ることで、目のかすみ、視力の低下、光をまぶしく感じるといった症状が現れます。高齢になるとほとんどすべての方が白内障になると言われています。
初期にはほぼ症状がないため、定期的な検査による早期発見・早期治療が大事です。治療は、点眼治療または手術が行われます。
ひらの眼科では白内障の治療について多くの経験のある院長が、それぞれの患者さんに合った治療法を提案いたします。
緑内障
緑内障は、眼圧の上昇などによって視神経が障害されて発症します。視野が狭くなったり、欠損したりといった症状が見られ、最悪の場合、失明に至る可能性があります。定期的に検査を受けて、早期発見・早期治療に努めましょう。40歳以上の日本人の20人に1人は緑内障があると言われています。40歳以上の方は、緑内障の検診のために年に1回は眼底検査を受けることをおすすめします。
網膜剥離
網膜とは薄い膜状の神経組織で、眼球内の内壁に接着する状態で存在しています。網膜剥離は網膜が内壁から剥がれてしまう状態を言います。
網膜に穴が空いてしまうことが原因で起こるタイプ(裂孔源性)と、穴がないのに網膜の裏に水が溜まることが原因で起こるタイプ(非裂孔源性)の2種類があります。
裂孔源性網膜剥離は前駆症状としての飛蚊症(ごみのようなものが飛んでみえる)から始まり、進行すると部分的な視野欠損、視力低下を起こし失明に至る危険性があります。
早期発見、早期治療が非常に重要ですのでこれらの症状がある場合は早めに受診して、眼底検査を受けましょう。
ひらの眼科では網膜剥離の診断や治療に長く携わってきた院長が的確な診断と治療を行います。
硝子体出血
硝子体とは目の中にある透明なゼリー状の組織です。わたしたちは目の外からの光が透明な硝子体を通過して眼底(網膜)に届くことで物を見ることができます。硝子体出血は、様々な原因で硝子体に網膜からの出血が溜まった状態をいいます。
出血よって光が通過しづらくなるため、飛蚊症を自覚したり、かすんで見えたり、視力が低下したりします。
主な出血の原因は、糖尿病網膜症、網膜剥離、網膜細動脈瘤、網膜静脈閉塞症などです。出血の量が多い場合は、出血を切除する手術治療に加えて原因疾患に応じた追加治療も必要になります。
ひらの眼科では網膜硝子体手術に長く携わってきた院長が、的確な診断と治療を行います。
糖尿病網膜症
糖尿病網膜症は、糖尿病の3大合併症の1つです。網膜とは、眼底にある薄い膜状の神経組織ですが、糖尿病網膜症は糖尿病によって網膜の血流が障害されることが原因でおこります。初期は自覚症状に乏しいですが、進行すると硝子体出血や黄斑浮腫によって飛蚊症や視力低下などの症状が見られます。硝子体出血に対しては硝子体手術を、黄斑浮腫に対しては抗VEGF薬の眼内注射が必要になることがあります。
糖尿病網膜症は、進行すると失明の可能性があるため、糖尿病と診断された場合は、内科だけでなく眼科の定期受診も併せて行うことが大切です。
黄斑上膜(黄斑前膜)
黄斑上膜は、黄斑部と呼ばれる網膜の中心部分に線維性の膜が生じる状態をいいます。
膜の収縮にともなって黄斑部が引っ張られることで、物がゆがんで見えたり、物が大きく見えたり、視力が低下したりします。症状の程度に応じて、膜を切除する硝子体手術が必要になります。
黄斑上膜は手術のタイミングが大切です。ひらの眼科では黄斑上膜の研究や治療に長く携わってきた院長が、それぞれの患者さんに合った治療のを提案いたします。
黄斑円孔
黄斑円孔は、黄斑部と呼ばれる網膜の中心部分に穴が生じている状態をいいます。硝子体という網膜に隣接するゼリー状の組織によって、黄斑部が引っ張られることが原因でおこります。
物が歪んで見えたり、視力が低下したりします。
気づかずに時間が経つと、治りづらくなり後遺症も残りやすいため、早期の硝子体手術によって円孔を閉鎖させる必要があります。
これらの症状がある場合は早めに受診して、眼底検査をうけましょう。ひらの眼科では網膜硝子体手術に長く携わってきた院長が、的確な診断と治療を行います。
網膜静脈閉塞症
網膜とは、眼底にある薄い膜状の神経組織ですが、網膜静脈閉塞症は高血圧・動脈硬化などが原因で、網膜の中の静脈が閉塞してしまう状態です。閉塞によって血流が悪化するため、網膜出血や黄斑浮腫などが起こり、視力が低下します。血流の悪化している網膜にレーザー治療をおこなったり、黄斑浮腫に対して抗VEGF薬の眼内注射をおこなったりする必要があります。高血圧などの生活習慣病をお持ちの方で視力低下を自覚した場合、早めに眼底検査を受けましょう。
加齢黄斑変性症
加齢黄斑変性は、網膜の中心にある黄斑部の加齢によって起こる病気です。黄斑部に異常な血管が生じることで、浮腫や出血が起こります。
代表的な初期症状に、視野中心部のゆがみや視力低下があります。
抗VEGF薬の眼内注射を定期的に行うことで、異常な血管を抑える必要があります。ゆがみや視力低下などの症状を自覚した場合、早めに眼底検査を受けましょう。